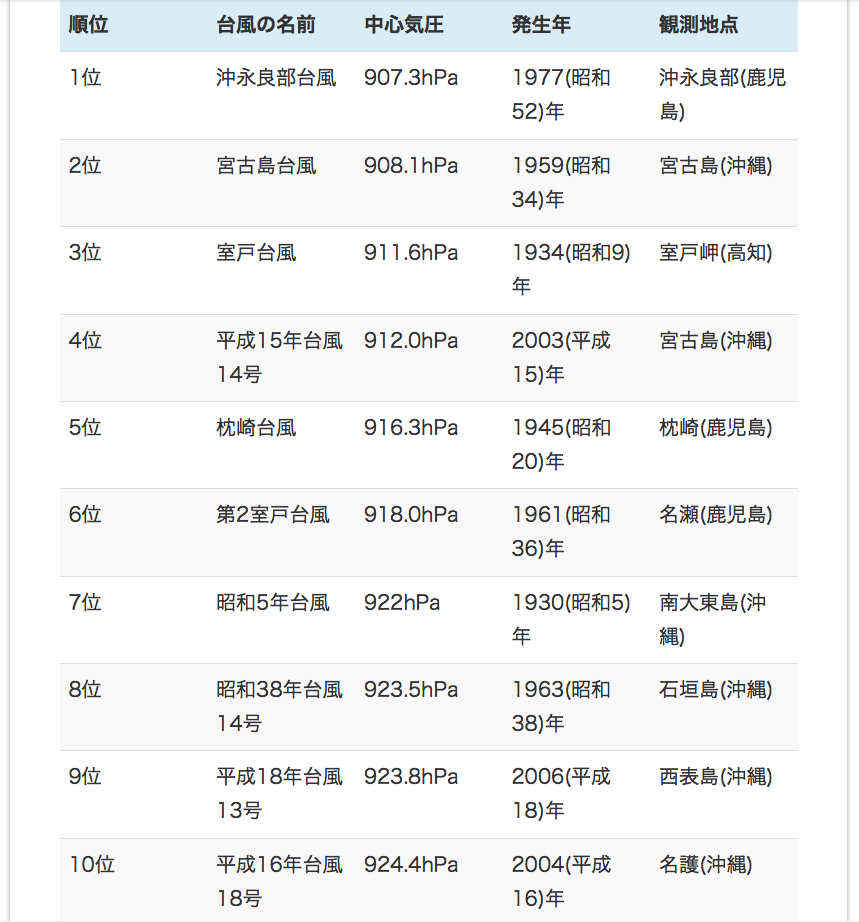9/3
台風9号何とかクリア、昨夜2時過ぎから4時頃までかなり強い風が吹いた。予想していたより弱かったとは云え、山の木が倒れたのではと見に行ったのだが、折れそうな大枝は全て南北側に出ていたため折れずに済んだようだ。 ゴーヤの棚も持ちこたえた、一安心である。とはいえ、さらに強い10号が週末に来るという。
もちろん、無傷だったわけではない。今が出荷の最盛期である白ナスと収獲期が近いトウガラシは多くの株が傾いていた。これは起こしておかないと後の収獲が続かない。朝から昨年潰れたゴーヤ棚で使っていた4mサイズの鋼管30本ほどを1.3mに切り、これを支柱として各植物の脇に打ち込んだ。後は支柱に植物を固定するだけなのだが、ハンマーを振り回し過ぎて肩が痛い。半分ほど固定して、明日に残した。明日できることを、今日するな。はは、師匠に怒られそうである。
暢気なことを書いていたら、またもや嫌なニュースである。【釜山聯合ニュース】より引用
台風で原発4基の稼働中断 原子炉は安全=韓国
記事一覧 2020.09.03 09:16SHARE LIKE SAVE PRINT
FONT SIZE
【釜山聯合ニュース】韓国南東部を襲った台風9号の影響で、釜山市にある原発4基の稼働が中断された。

台風9号の影響で釜山市内の原発4基が停止した。(左上から時計回りに)新古里原発2号機、1号機、古里4号機、3号機(資料写真)=(聯合ニュース)
原発を運営する韓国水力原子力(韓水原)の古里原子力本部は3日、この日明け方に古里原発3、4号機と新古里原発1、2号機の原子炉が停止したと発表した。
原子力安全委員会は韓水原から原子炉の自動停止について報告を受け、専門家からなる調査団を派遣し調査を行っている。
古里原子力本部は、原子炉停止の原因が発電所外部の電力系統の異常と推定しており、原因を調べている。
原子力安全委は、原発4基が安全停止状態を維持しており、放射線レベルも平常時の水準を維持していることを確認した説明した。
hjc@yna.co.kr
外部電源の異常、4基全部停止、放射線レベルは上がっていないだって。こんな場合、政府は必ず嘘をつく。パニックが起こっては収容が付かなくなるので、それはどの国の政府であっても同じである。原発4基が安全停止状態を維持しているという云い方は、野田首相が言った冷温停止状態にあるという云い方と同じである。なんか嫌な予感が?
写真を見ると海岸にあり、標高は低そうだ。とすれば台風9号による洪水ではなく、高潮あるいは風による送電線の切断あるいは送電用鉄塔の倒壊が原因だろう。3日後に、より強い10号台風がほぼ同じコースで襲来する。本当に大丈夫なのだろうか?
現在、ヤフーニュースにもグーグルのニュースでも捜すのが難しい。朝のニュースなのでキーワードで検索をかけないと分からないだろう。大事故になれば日本への影響は大きいことが予想される。夕方までは、重要なニュースとして扱うべきではないか。
中央日報のニュースがグーグル上にあった。以下の通りである。
2020年9月3日 7時50分
ざっくり言うと
3日、台風9号の影響で韓国の原子力発電所4基の稼働が停止した
原子力本部は、発電所の外の電力系統異常と推定して原因を分析中
発電所は安全に停止し、放射線の漏出などもない状態とのこと
台風9号で韓国古里原発4基も停止…「安全上の問題なし」
2020年9月3日 7時50分
中央日報
韓国釜山(プサン)を強打した台風9号「MAYSAK(メイサーク)」の影響で、原子力発電所4基の稼働が自動で中断した。
韓国水力原子力古里(コリ)原子力本部は3日、「運営中だった古里3、4号機、新古里(シンゴリ)1、2号機の原子炉が未明に停止した」と明らかにした。
新古里1号機がこの日午前0時59分ごろにまず最初に停止し、次いで新古里2号機が午前1時12分ほどに止まった。古里3号機は午前2時53分、古里4号機は午前3時1分ごろに自動停止した。停止した原発はどれも発電を止めた状態だ。
古里原子力本部は、原子炉の停止原因が発電所の外の電力系統異常と推定して原因を分析中だ。
原子力安全委員会によると、発電所は安全に停止し、放射線の漏出などもない状態だ。2017年に永久停止した古里1号機と現在整備中の古里2号機にも非常ディーゼル発電機が自動で作動して安全上の問題はない状況だと付け加えた。

にではなくて「で」ではないか? 明確に書いてないけど、外部電源の喪失を意味しているようだ。でとすれば、自動停止した4基についても非常用電源による冷却が行われている事を意味する。とすればこれは緊急停止であり、F1事故と同じである。非常用ディーゼル発電機が正常に動き、かつ燃料が十分に補給されることを願っている。